- 健康医学 面白ゼミナール
- 2025.08.20
某新聞の投書欄に、「水泳の授業は大切だ」との14歳の中学生徒の意見が掲載されていた。昨今、学校プールの老朽化や熱中症のリスク、教員の負担、指導の難しさなどが理由で、水泳授業を廃止したり、民間委託する動きが広がっている。学習指導要領には、「小学1年生~中学2年生は水泳の実技が必修」とされている(水泳場の確保が困難な場合には水泳指導を行わないことができる)。

基本的には、水泳は体育の一つの教材・技能として指導する面があるが、他の陸上競技、球技や体操競技などと決定的に違うのは、「命を守る技能」であることだ。先に紹介した投書でも、「(水泳の授業がなくなれば)水による事故に対処できなくなってしまう」ことを生徒自身が訴えている。
体育は、からだを育む教育であり、水泳は心身の発育・発達に重要な効果を有するとともに、万一、川・海・湖・池などに落ちた時に、溺れるのを防ぎ、自らの命を守るための技能となるものだ。

ところで、最近子どもがプールでおぼれて死亡する事故が目立っている。中には、学校の水泳の授業中、スイミングクラブでの遊泳中に、教師や指導者がその場に居る中で、小学生や幼児が溺れて命を失う痛ましい重大事故(「業務上過失致死容疑が問われているので、「事件」でもある」が起きている。
これらの事故については、種々の発生要因があげられるが、予防の観点から重要なことは、二つ。
第一に、泳げる人もおぼれること。
第二は、子どものおぼれは、おぼれているようには見えないことだ。
前者については、ノドに急に水が入って、迷走神経反射を起こして心臓の働きが弱り、脳への血流が減少して、意識がなくなるメカニズム(「気管内吸水」)と、潜水前に過呼吸をして泳ぎ始め、体内に二酸化炭素がたまって息苦しくなる前に、酸素が消失して急に(パニック状態がなく)、意識がなくなる(ブラックアウト)メカニズムが知られている(日本水泳連盟編集『水泳プールでの重大事故を防ぐ』、ブックハウスHD、1989年に詳述)。
後者については、旧知の日本のライフセービングの生みの親である救急救命学者の小峯 力中央大学教授が、今春、ある会議で紹介してくれたプールでの子どもの溺れの実際の映像が明確に示してくれた。沢山の子どもや大人たちの中で、男の子が遊泳しているように見えるが実はすでにおぼれかけていて、ごく近くにいた大人たちが誰も気づかなかったという重要な記録だった。
| 一般的な「溺れている」イメージ | 静かに「溺れる」こともある |
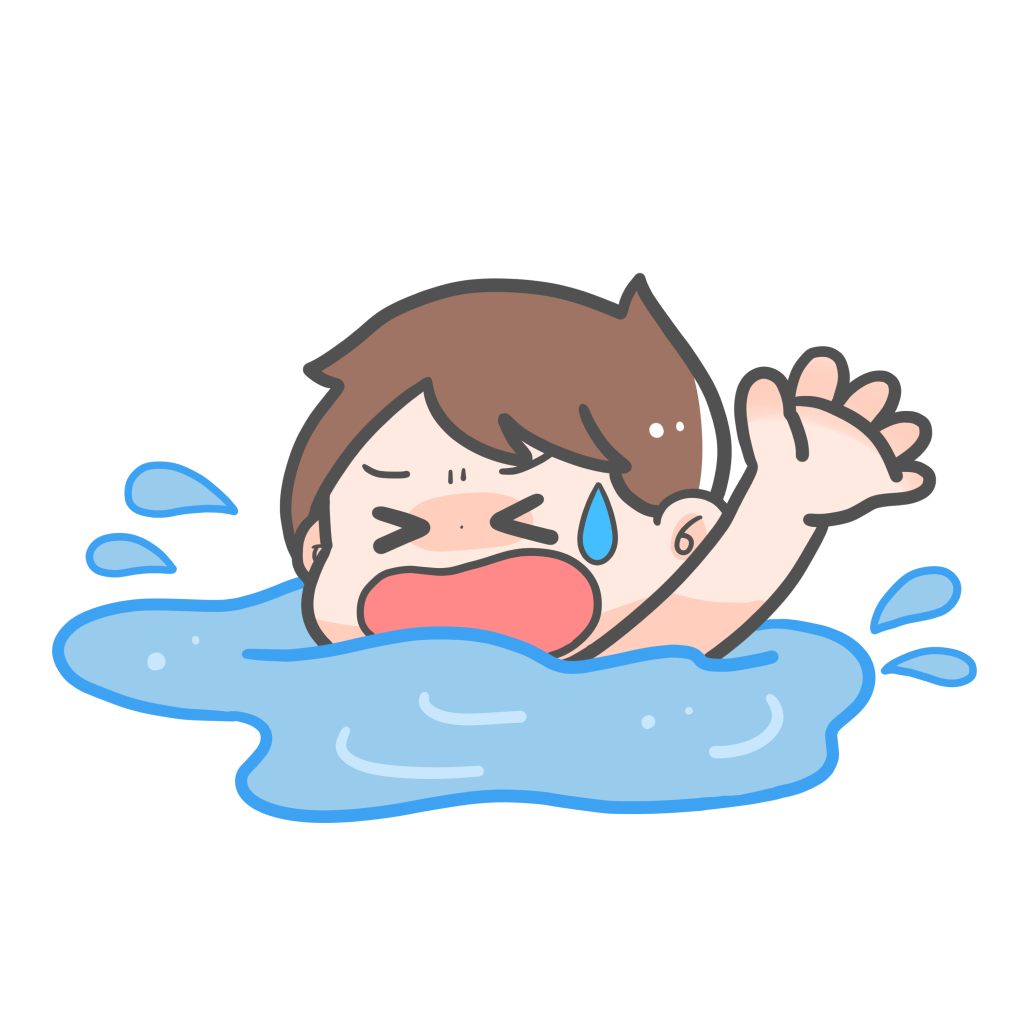 |
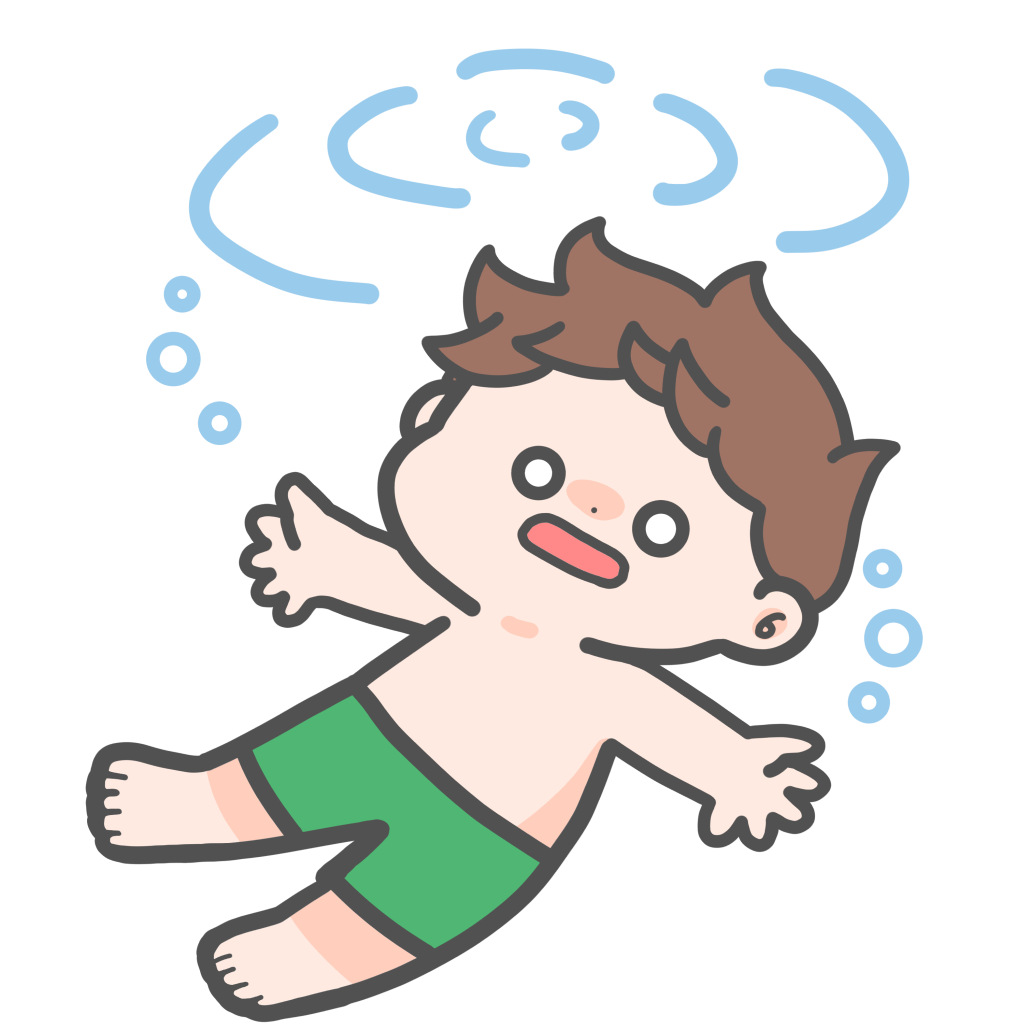 |
酷暑の今夏(きっと9月も暑い)、本来、水遊びが大好きな子どもたちは、是非水の中で楽しい時間を過ごしてほしいと願うとともに、いつか是非、水泳をしっかり身につけてほしい。しかし、水の中は、地上とは違った大きなリスクがあることを、子どもたちも大人たちも決して忘れないように。
執筆者:武藤芳照
(東京健康リハビリテーション総合研究所 所長 / 東京大学名誉教授 / 医学博士)
詳しいプロフィール
